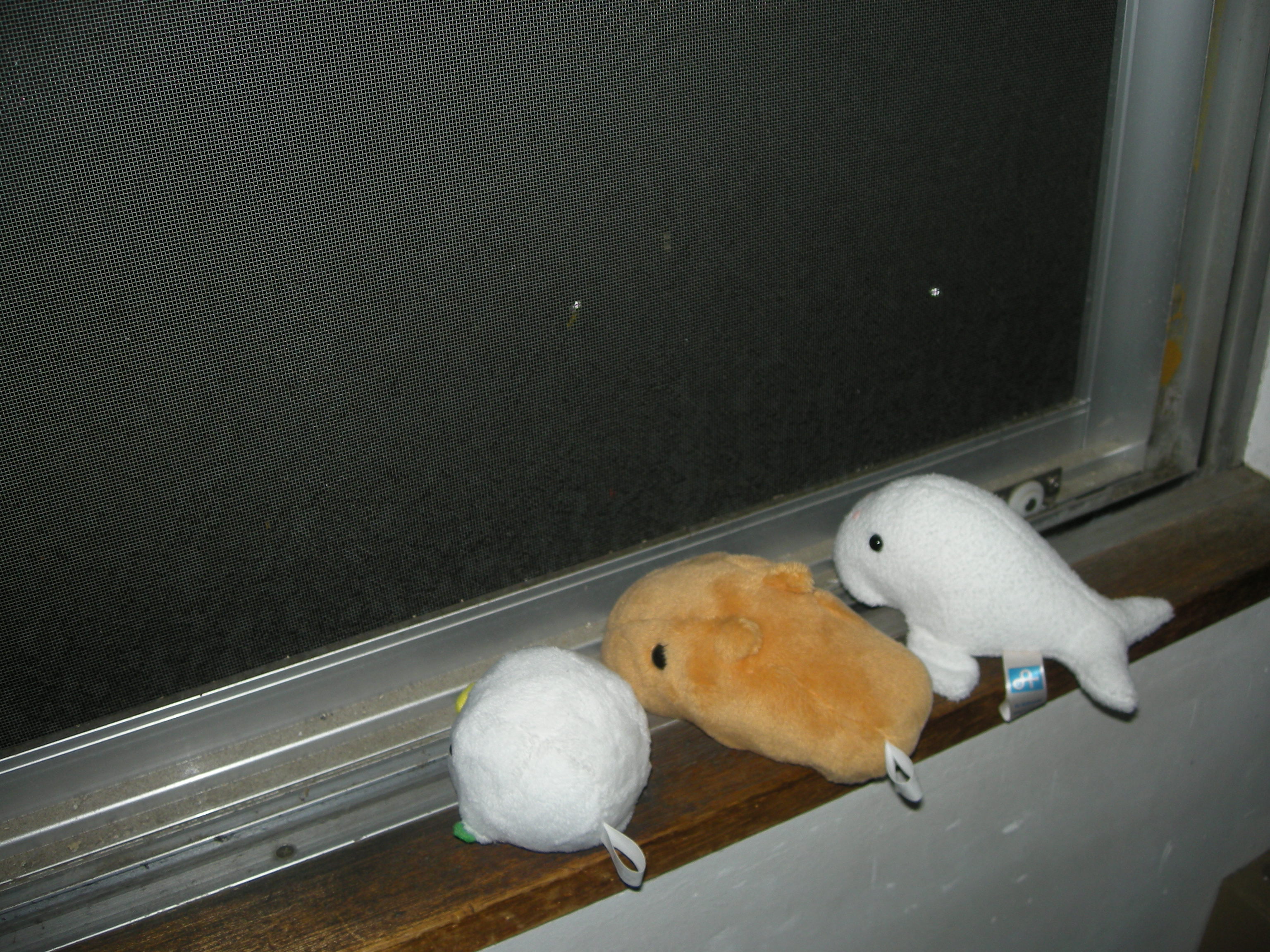
大気光の研究
[Japanese / English]
大気光という言葉を初めて聞いたかもしれません。
大気光は、「肉眼では見えないほど弱く大気が光っている現象」です。体感できるとすれば…、月明かりがないときに最初は星空しか見えなくても、だんだん周りの山が うすぼんやり見えてくるとき、でしょうか。もっともこれも「大気光」だけが原因というわけではなく、星明かりや宇宙空間のちりで散乱された太陽光の影響もあると考えられています。 とにかく、肉眼ではわからないくらいに弱い光です。
街の中でお外を見ても、大気光はわからないと思います…
大気光もオーロラ同様に大気中の粒子のエネルギーの放出が関わっています。大気光は、原子や分子が昼間にたくわえたエネルギーを夜の間にじわじわと光として放出する現象です。 酸素原子がたくわえたエネルギーは緑色(波長557.7nm)の光として放出されます。微弱な大気光をとらえるのには「大気光イメージャ」という観測装置が 用いられています。
以前から大気光には、地上86km付近では水酸基が赤く発光する層、地上96km付近では酸素原子が緑色に発光する層、といった「層構造」があるといわれています。しかし、これまでの 観測の多くは地上からの観測でした。
研究では「れいめい衛星」が観測した大気光のデータを解析します。地上で用いられる「大気光イメージャ」に対し、れいめい衛星は650km上空から地球の縁(リム)の方向をむいて大気光を 観測します。中低緯度領域の上空の大気光の鉛直構造および垂直構造をれいめい衛星の観測から定めることを考えています。